|
|
|
|
| ■昭和女子大学附属幼稚園とは? |
| ■沿革 |
創立者 人見圓吉 |
| 大正15年 |
附属幼稚園を設置 |
| 昭和 3年 |
夏季寮開設(館山) |
| 13年 |
田園学寮開設(武蔵野・湘南) |
| 20年 |
世田谷区太子堂(現在地)に校舎移転 |
| 26年 |
昭和幼稚園を開設 |
| 28年 |
幼稚園から大学までの一貫教育体系が完成 |
| 31年 |
児童教育研究所開設 |
| 35年 |
初代幼稚園長の勇退により、人見楠郎が第二代園長となる |
| 38年 |
学校法人昭和女子大学に学校法人昭和高等学校を併合 |
| |
学校名を昭和女子大学附属昭和高等学校、附属昭和中学校、 |
| |
附属昭和小学校、附属昭和幼稚園と改める |
| 42年1月 |
幼稚園新園舎竣工 |
| 49年 |
人見楠郎第二理事長就任 |
| 52年 |
研修学寮「東明学林」を開設 |
| 55年2月 |
創立者を記念し人見記念講堂を開設 |
| 61年 |
研修学寮「望秀海浜学寮」を開設 |
| 62年 |
研修学寮「会津キャンプ村」を開設 |
| 平成 3年 |
昭和幼稚園開園40周年式典を挙行 |
| 6年 |
光葉博物館開設 |
| 12年 |
人見楠郎第二代理事長逝去 |
| |
人見楷子第三代理事長就任 |
| 13年 |
昭和幼稚園開園50周年式典を挙行 |
●幼い頃の導き方ひとつで、人生が開花するかが決まります。
昭和女子大学附属幼稚園には、毎日の生活を楽しみながら、未来の可能性の種をまき、
すこやかに育てる、かけがえのない日々があります。
|
|
|
学内風景 |
学内風景 |
学内風景 |
|
|
|
学内風景 |
園舎 |
幼稚園シンボルの鐘 |
|
|
|
|
|
明るいエントランス |
明るく広い廊下 |
遊戯・音楽・運動何でも出来ます |
|
|
| ■教育の目標 |
○幼稚園は、将来のための土台を作る大切な時期。
だから、5つの目標を立て、子どもたちのバランスのとれた成長をはかります。 |
|
|
|
まず、健康なからだをつくります。正しい栄養と太陽の下での十分な運動、しっかりと休養をとることが大切です。そこで幼稚園では完全給食を実施し、広い庭園とさまざまな遊具を活用して体力の増進をはかります。
|
|
すすんで友だちに親切にする心の芽を育みます。どんなことでも友だちと協力することから始まって、約束を守り、人のことを思いやる気持ちを育みます。
|
|
|
|
体験を通して、自ら考える力を身に付けます。知りたいという意欲をもち、自分で工夫をこらし、実際にやってみることから、判断力や創造力が大きく成長するからです。いつも自分の考えているうちに、園児は生きた知識を身につけ、新しいアイデアを生み出す、のびのびした力をそなえるようになっていきます。
|
|
人のためにも役立とうとする、たくましさを育てます。自分のことだけでなこ、社会のためにも役立とうとする、たくましい心身を育むために。自分の足で歩き、自分の手で作る経験は、園児たちの輝かしい将来の基礎となります。
|
| |
|
|
| |
やり始めたら最後までがんばる意志を育てます。幼児期には、自分でやるべきことは、他人に頼らずりっぱにやりとげる経験を積ませたいものです。昭和幼稚園には、子どもたちにとって貴重な体験の場が限りなく存在します。 |
|
|
| ■
|
|
| 住所・最寄り駅 |
|
|
|
| ■
住所 |
〒154-8533 東京都世田谷区太子堂1-7
|
■
最寄り駅 |
●東急田園都市線「三軒茶屋」駅 徒歩7分 |
|
|
|
| 特 徴 |
○幼稚園は、将来のための土台を作る大切な時期。
だから、5つの目標を立て、子どもたちのバランスのとれた成長をはかります。 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
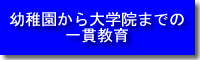 |
| ■大切なのは、自ら考え、行動すること。 |
| 毎日の生活の中に、想像力を伸ばす工夫があります。 |
| ▲完全給食制度。 |
| ▲併設昭和中学・高等学校の生徒が毎日手伝いにきてくれる「幼稚園庶務制度」の実践。 |
| ▲11月の「昭和祭」での発表。 |
| ▲学園施設「東明学校」での体験学習・宿泊保育。 |
| ▲学園施設「会津キャンプ村」での親子・家族でのキャンプ体験保育 |
| ■小学校との交流。 |
| ▲小学校の先生による授業の実践。年長組と小学1年生との交流の実施。 |
| ▲一貫校ならではの幼少一体教育(図工・理科・英語教育)。 |
| ■「文部科学省指定大学」ならではの一貫教育モデル教育を実践。 |
| ▲小学校の卒業生は中学・高等学校へは学力試験免除制度があります。 |
| ▲中学・高等学校のカリキュラムを集約し、最終学年では女子大の授業に参加できる「五修生制度」 |
| があります。 |
| ■「母の会」の充実 |
| ▲園児を育むための「母の会」を教師と家庭が同じ気持ちで充実させています。 |
| ▲講演会・手芸・陶芸などの活動を通じて、お母さん同士の親睦と研修をはかっています。 |
| |
| |
|
|